洋風の家が増えてきた近頃では、畳よりフローリングのお部屋が主流になってきました。
畳には畳の良さもありますが、どこか古臭く感じたり、オシャレでイマドキな部屋のイメージに合わないことも多いでしょう。
そして、畳は物を置けば沈んで跡がついてしまいます。
古くなればささくれや色褪せも目立ってくるなど、メンテナンスの上でも面倒だと感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし、賃貸住宅では原状復帰のことを考えなければいけないし、傷をつけたり、大がかりなリフォームは出来ません。
また、集合住宅では、大きな音は近隣への配慮が必要です。外した畳をしまっておくにも場所をとります。
そして、何より費用も気になる・・・。
このように、畳からフローリングにリフォームするには、問題がいくつもあります。
そんな方のために、この記事では
- 畳をフローリングにリフォームする方法
- DIYでお手軽にフローリングにする方法
をご紹介していきます。
■目次
畳をリフォームしてフローリングにする工法
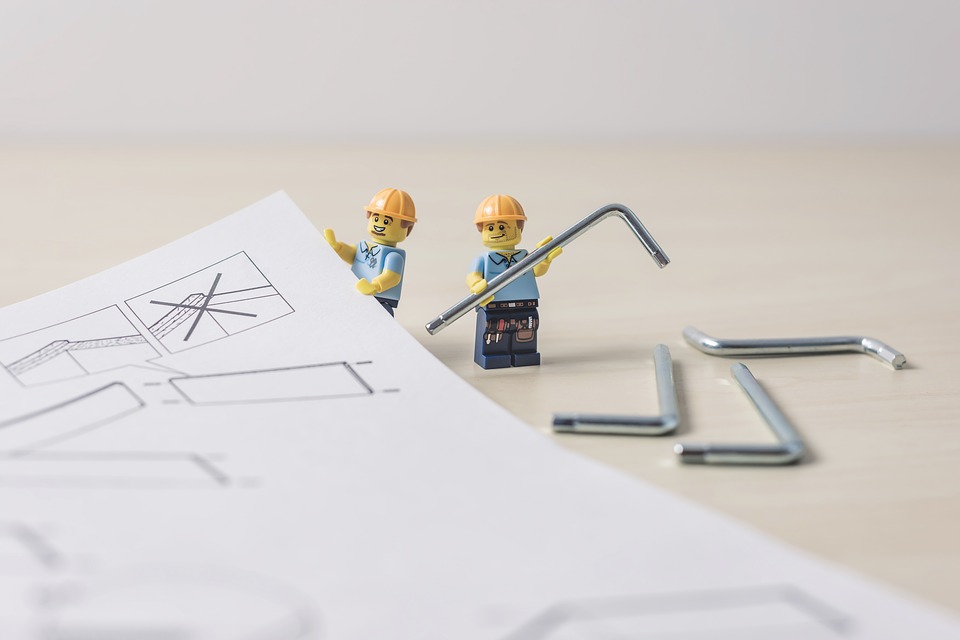
通常、フローリングにするには2通りの工法があります。今回は簡単に施工方法に触れながらみていきます。
張り替え工法
既存の畳を剥がし、フローリングを張る方法です。
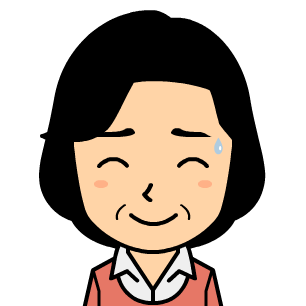
コーキング剤?巾木?

コーキング剤は主に壁紙の隙間とかに使われる穴埋め材のことなんだ。
巾木っていうのは、壁と床が接する角のところにカバー材だよ。
隙間を埋めるだけでなく、部屋の美観も良くなるし、何より壁が傷むのを防いでくれるんだ。
重ね張り(上張り)工法
つづいて、重ね張り工法です。こちらは、今ある床に床材を直接置いていきます。
1.下地をきれいに平らにする
まずは、下地をきれいに掃除をします。
その後、下地に凹凸や勾配がないか確認し、平らになるようにセメントやシートで調整します。
これを不陸調整といいます。
2.フローリングを張る
ここからは、張替えの手順と同じです。
仮置きをして、部屋の構造に合わせてカットします。仮置きが終わったら、接着剤や釘を使いながら、フローリングを張って固定していきます。
最後の一段は壁に当たって入りづらいので、端を斜めにカットして押し込むように入れると入ります。
3.(任意)コーキング剤と巾木で隙間を埋めて完成
こちらも、張替と同じように隙間を埋めていきます。
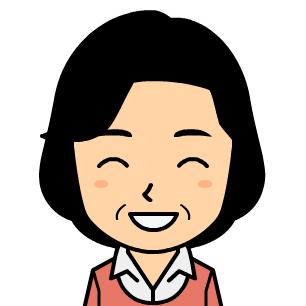
あら、重ね張りのほうがだいぶ簡単そうね。

そうだね。床を剥がす作業がない分、時間もかからないし、廃棄処分の費用も必要ないんだ。
でも、畳にボンドを直接塗るわけにもいかないから、結局張り替え一択になってしまうね。
お手軽にフローリングに出来るDIYはないの?

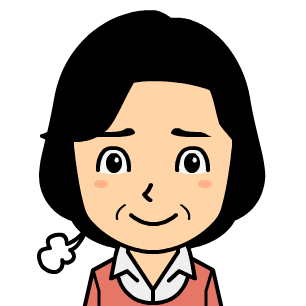
そんな……。じゃあ、畳をフローリングにするには、やっぱり大掛かりな工事をするしかないのね。
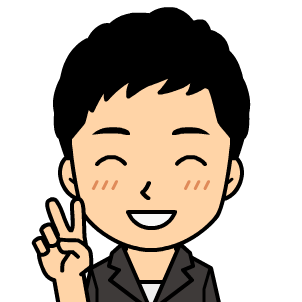
いやいや、最近はとっても便利なものがあるんだよ。
本来はボンドなどで接着したり、釘を打ち込んだりして固定していきますが、最近は「置き敷きタイプ」といって接着や釘を必要としないタイプもあります。
こちらのほうが、ボンドを使わない分、原状復帰させなければならない賃貸住宅には向いていますし、畳をしまっておく必要もありません。
また、難しい施工を必要としないので、DIYでも十分出来ます。
ですが、畳の上に直接フローリングを置いてしまうと、畳にカビたり、床材が浮いてしまって危ないなどの理由から、置き敷きタイプでもメーカーが嫌がるのが現状です。
そのような状況の中でも、畳の上からでも敷けるとメーカーが推奨している「置き敷きタイプ」のフローリング材を集めてみました。
置き敷き用フローリング
イージーロックフローリング(無垢床フローリング)

天然の木で出来たフローリングです。はめ込み部分を特殊な構造にすることによって、はめ易いのに外れにくい構造を実現しました。
厚みは1.5㎝と少し厚いですが、本物志向にこだわりたい方にはうってつけのフローリング材です。
価格:¥5,480/㎡~
床タイル
クリックオン プレミアム

こちらは塩化ビニールのフローリングですが、エンボス加工が施され、まるで本物と見間違えるほどのしっかりしたつくりになっています。
厚みが4.5mmと大変薄く、カッターでカットすることができ、1枚1㎏程度と軽いので、施工の簡単さもおすすめする理由です。
価格:¥6,500/㎡~
ウッドカーペット
GA-60

合板で出来たカーペットです。普通のカーペットと同様に敷くだけで、あっという間にフローリングに早変わりします。
気になる価格もかなりリーズナブルになっています。
価格:¥1,700/㎡~
上手に畳をフローリングにDIYするコツ

不陸対策(レベリング)
不陸(ふりく、ふろく)とは、建築用語で床などが「凸凹や勾配など平らでないこと」を指します。
不陸を調整しないと、フローリングが安定しないだけではなく、フローリングに隙間が出来てしまい、引っかかって怪我をしたり、床鳴りの原因になったりします。
通常、床材の接着剤をきれいに剥がし、下地調整材と呼ばれるセメント系のパテなどで埋めて慣らします。
しかし、畳の上にフローリングを置く場合は、そのようなことは出来ません。
その場合、下地調整シートを下に敷くことで、調節が可能です。

こちらの「テプレックス」という商品は、不陸調整だけではなく、通気性や調湿性もあるのでおススメです。
カビ対策
本来、畳には調湿機能があります。
畳の材料であるイグサは、湿度が高くなると湿気を吸い、冬場の乾燥した時期は湿気を吐き出します。
その畳の上に直接フローリングを敷いてしまうと、畳は湿度が高くなり、通気性も悪くジメジメした環境になるので、カビが生えやすくなります。
対策はいくつかあります。
- 部屋の湿度を下げた状態を施工する
畳が湿気を多く含んだ状態での施工は避けましょう。
夏場や晴天など畳の湿気が少ない時を狙って施工することで、フローリングの下の湿度を下げることができます。
事前に畳干しをしたり、除湿機などで湿度を下げましょう。
- 下地材を調湿性のあるものにする
防湿性のみの下地調整シートでは床下から上がってきた湿気は、畳表にたまってしまいます。
これでは、畳表はかびてしまいます。
この点でも、先ほどご紹介した「テプレックス」は調湿性も兼ねそろえており、おススメです。
また、ホームセンターやネット通販で防カビシートが売られています。こちらを畳の上に敷くことで、カビを生えにくくする効果が期待できます。
- 風通しをよくする
部屋の換気を頻繁に行なうことで、カビが生えづらくなります。
また、年に一度はフローリングを上げる、畳干しをするなど、フローリングの下の通気性をよくすることで湿度をさげましょう。
床が上がることを考慮する
床が上がることで、様々な弊害が出てくることがあります。
例えば、部屋と部屋の間に段差が出来てしまう、扉が床材にぶつかってしまうなどです。
また、キッチンなど備え付けの家具は、床が上がることで作業スペースが低くなってしまいます。
この場合は、フローリングを置き敷き専用の薄いタイプを選ぶか、ぶつかった部分を削ったり、段差にスロープを付けたりすることで解消できるでしょう。
畳の大きさに気を付ける
地域によって、畳の大きさが違うことはご存じでしたか?
主に、江戸間・京間・中京間・団地間といった4種類があります。
〇畳の大きさ
| 団地間・五六間 | 江戸間・五八間 | 中京間・三六間 | 京間・本間 | |
| 1畳サイズ | 85㎝×170㎝(約1.45㎡) | 88㎝×176㎝(約1.5㎡) | 91㎝×182㎝(約1.7㎡) | 95.5㎝×191㎝(約1.8㎡) |
| 6畳サイズ | 255㎝×340㎝(約8.7㎡) | 264㎝×352㎝(約9.3㎡) | 273㎝×364㎝(約10㎡) | 287㎝×382㎝(約11㎡) |
6畳サイズにもなると、大きさの差は歴然で、京間の6畳は団地間では8畳程度に相当します。
フローリングや床タイルでは枚数が代わってきますし、ウッドカーペットでは足りなかったり、逆に余ってしまうなんてことになります。
また、関東だから江戸間、関西だから京間など地域によってはっきりと分かれているわけではありません。
ですから、畳の枚数で換算するのではなく、実寸でどのくらい必要なのか計算することが大切です。
突き上げ・目すき対策
フローリング材は、熱によって伸縮します。気温の高い夏場や湿気の多い梅雨時は伸び、気温の低い冬には縮みます。
このため、伸縮する余幅を持たせておかなければなりません。
余幅を持たせず、夏場に伸びた床が上に盛り上がってしまった状態を「突き上げ」、冬に収縮してはめ込み部分の隙間が開いてしまった状態を「目すき」といいます。
このようにならないためには、フローリングを張っている際に、はめ込み部分に名刺程度の厚さのもの(スペーサー)を挟むといいでしょう。
畳から憧れのフローリングへDIYする方法のまとめ
畳を剥がしてフローリングに張り替えることは、簡単ではありません。業者を必要とするような大掛かりなリフォームになってしまいます。
賃貸ではそこまではなかなか難しいですし、マンションなど集合住宅であれば工事の際の騒音が気になるなど、ハードルが高いです。
ですが、畳の上に置くだけの置き敷きタイプなら、そんな悩みとも無縁です。
上手に畳をフローリングにリフォームするコツでお話しした、
- 不陸対策
- カビ対策
- 床が上がることを考慮する
- 畳の大きさに気を付ける
- 突き上げ・目すき対策
にさえ気を付けておけば、自分でDIYすることができます。
畳の上から敷けるものは数が限られてしまいますが、それでも、色々な特徴を持った商品があります。
ぜひ、ご自分のイメージに合った素敵なフローリングを見つけてみてくださいね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
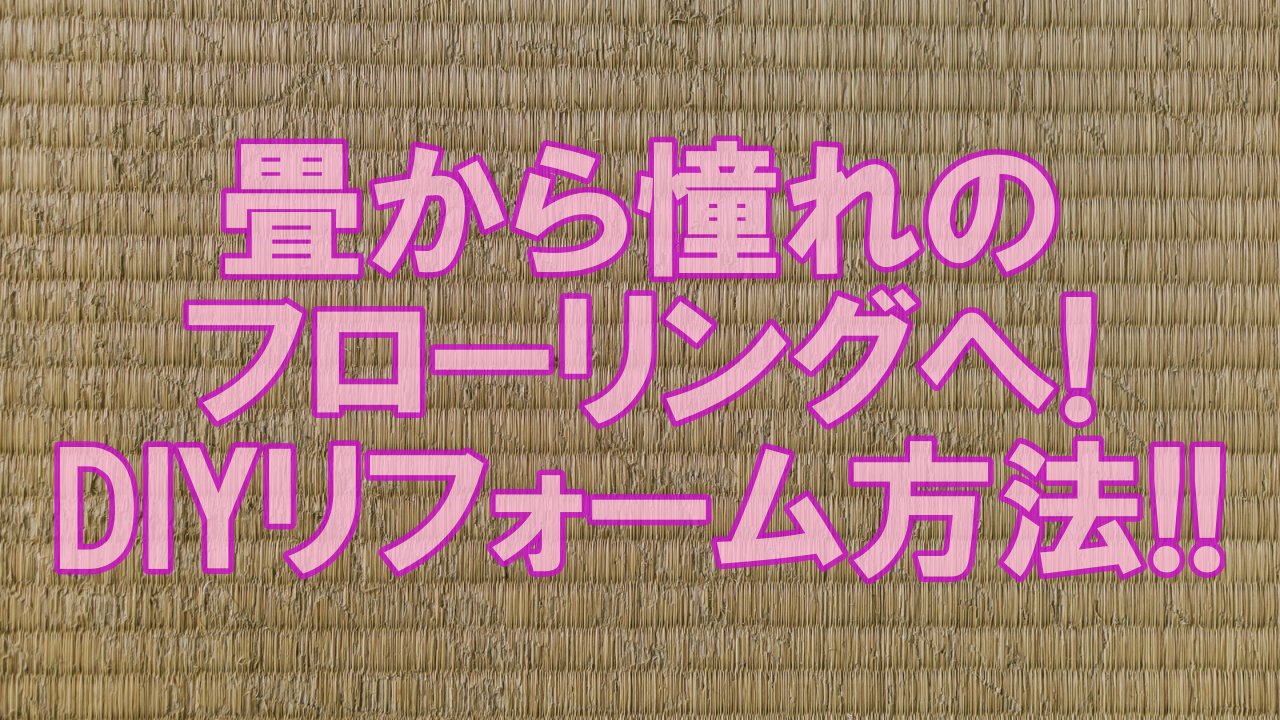
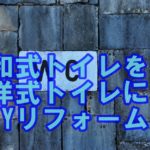


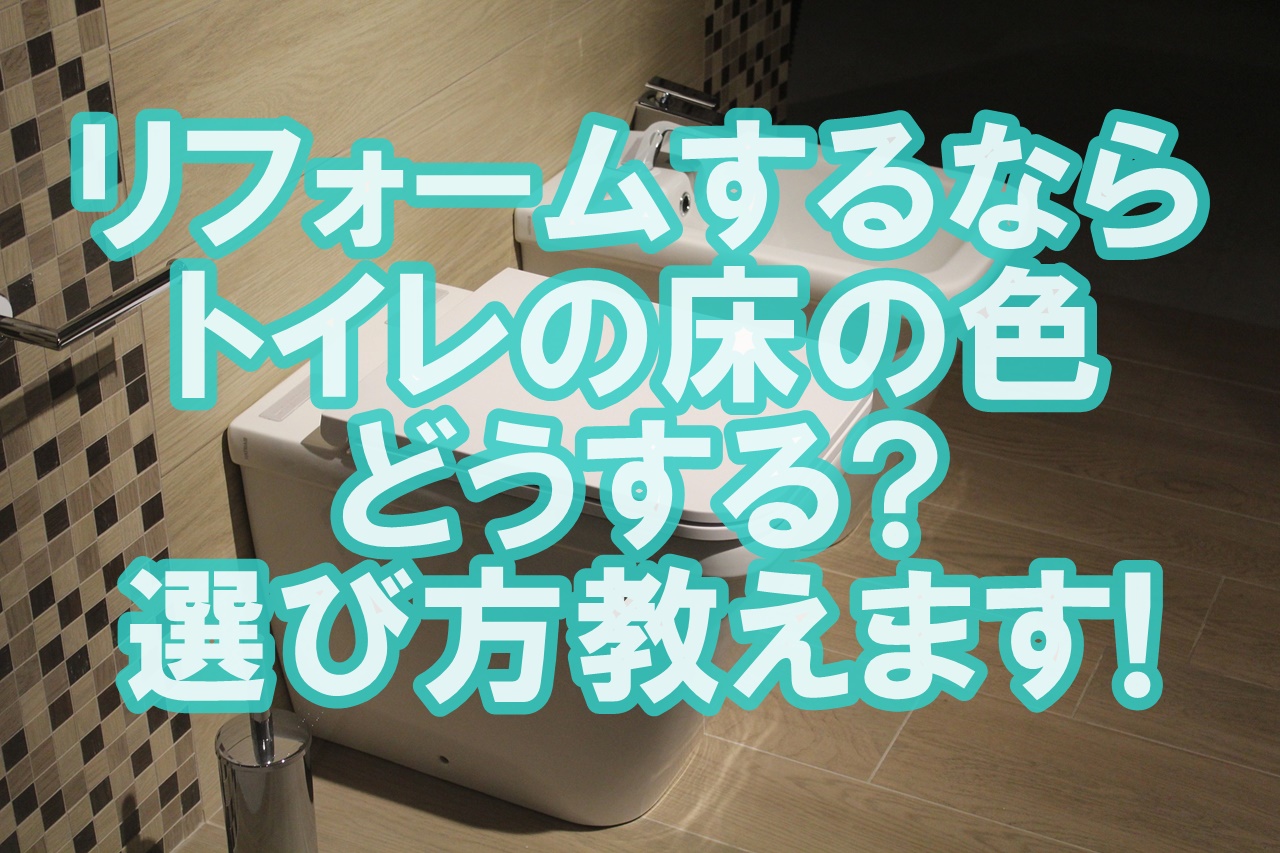
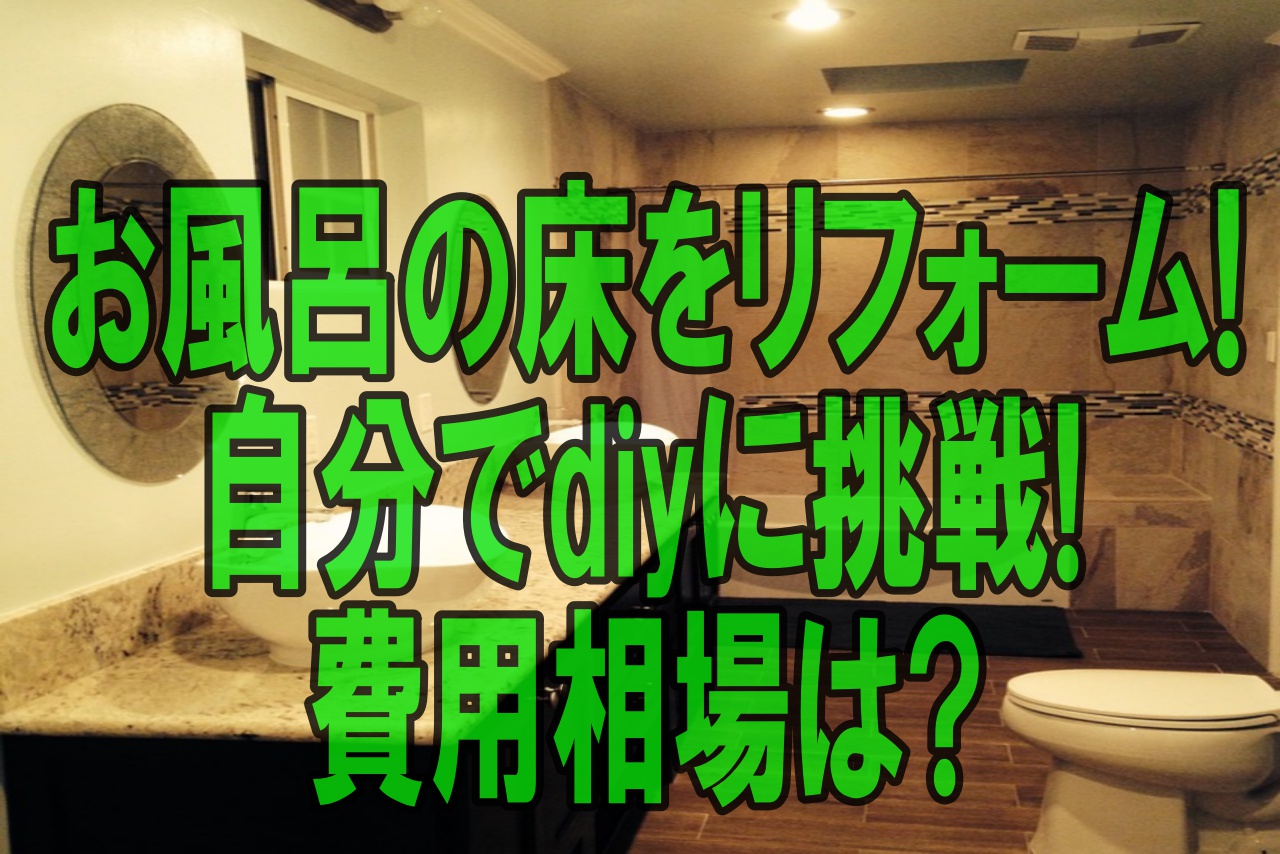
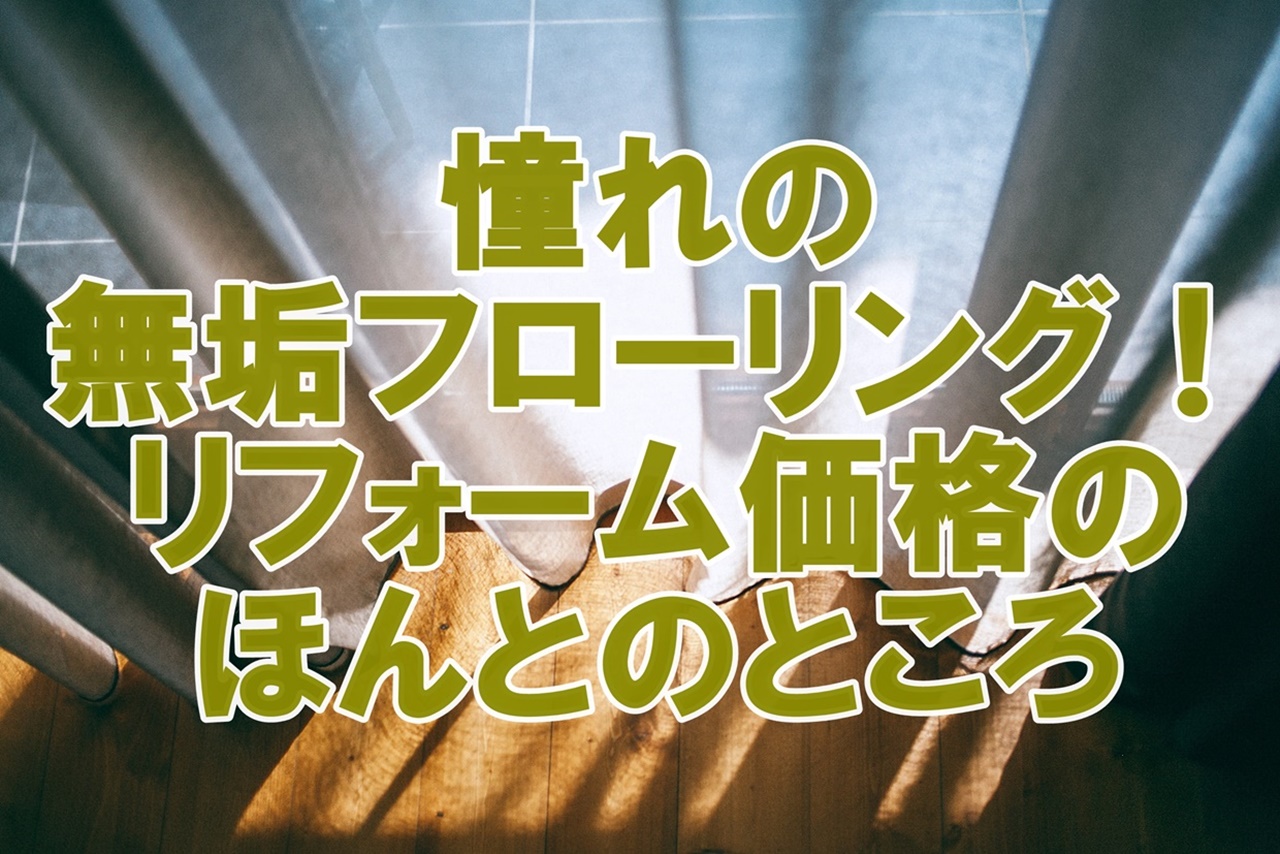
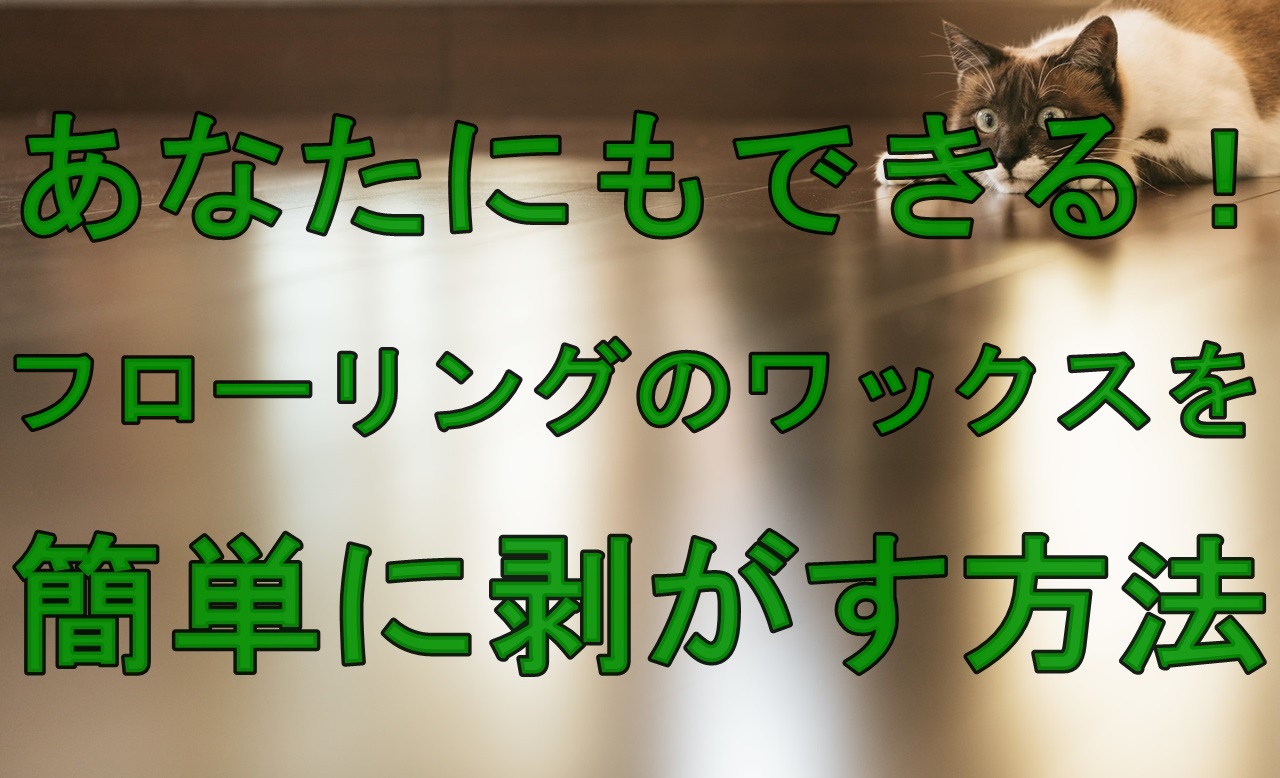

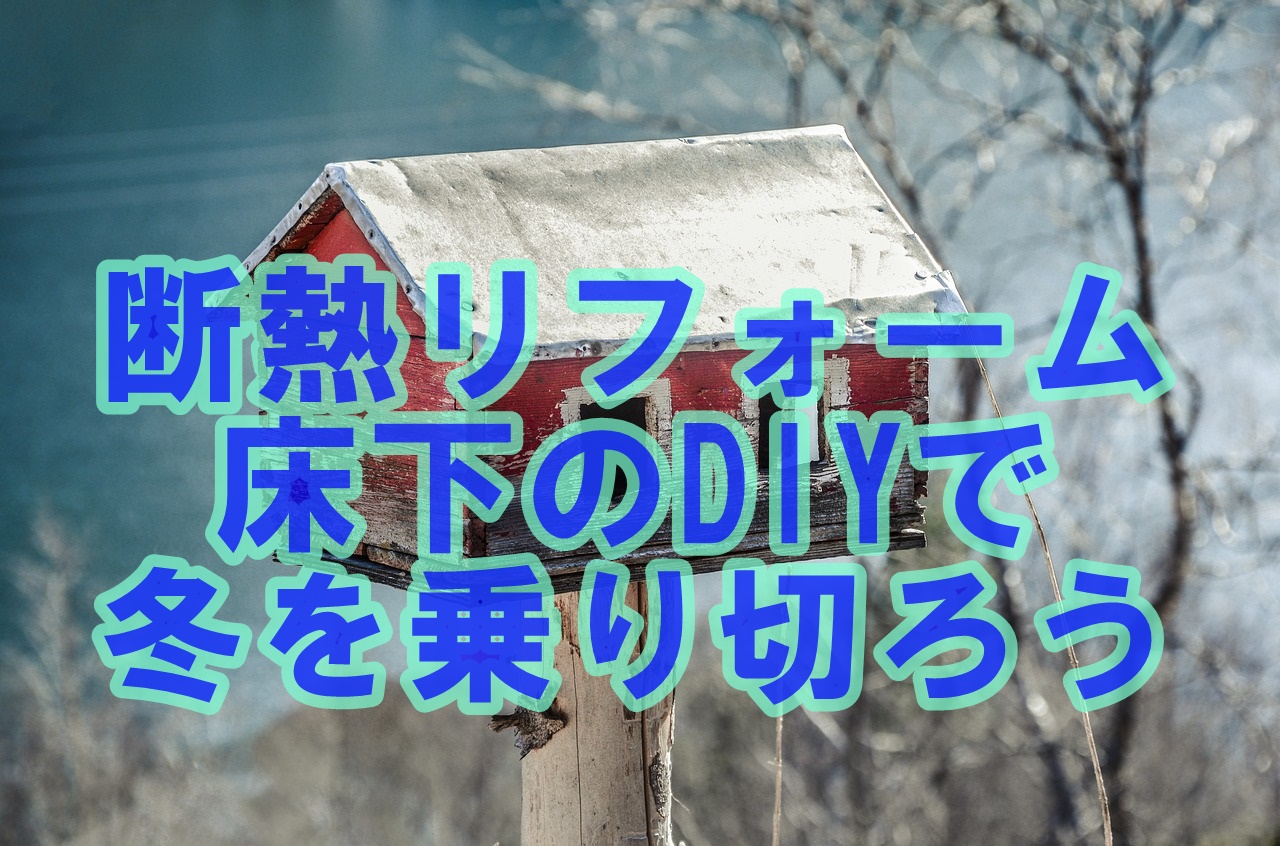
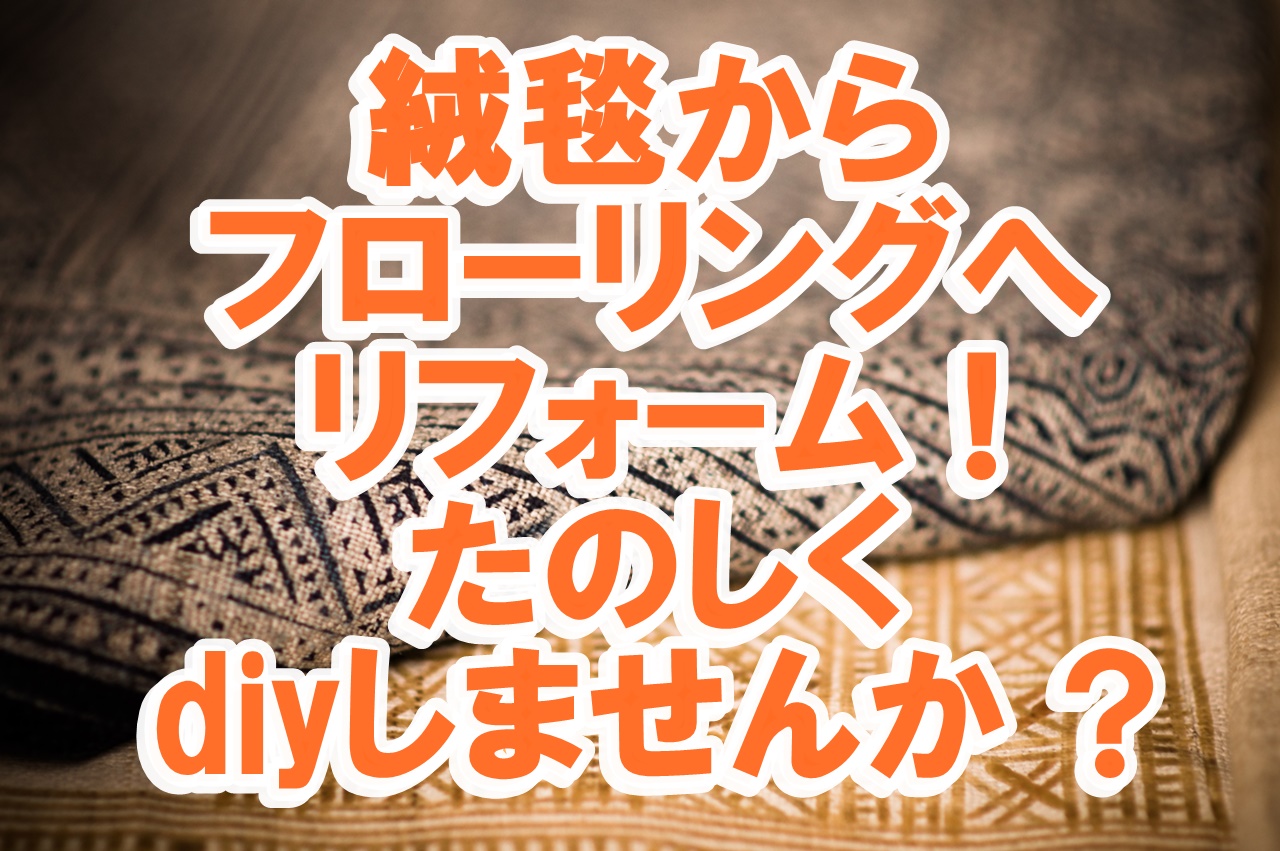







1.畳をドライバーなどで剥がす
畳下には床板があります。しかし、その上にすぐにフローリングを張れません。
フローリング材の厚みは1.5~3㎝、畳は5.5~6㎝のため、床板に直接張ってしまうと、2㎝~4㎝程度の段差が出来てしまいます
2.根太(ねだ)という床板を支えるための角材を置く
根太を置くことで、床下のかさ上げをします。
また、その間に断熱材を入れることで、フローリングでも暖かさを保てるようになります。
3.(任意)合板を張る
最近は、強度を高めるため、また床下からの湿気を防ぐために合板を張る方法が主流になっています。
この工法を「捨て張り工法」といいます。
これに対して、根太に直接フローリングを張る方法を「根太工法」といいます。
3.仮置きをする
部屋に敷き詰めて、どの板をどこに置くかを考えます。
1段目を置き終わったら、2段目は1/2~1/3ずつずらすように置きます。端にくる板を寸法に合わせてカットします。
最終段の板をはめ込む時、極端に細くなってしまう場合には、1段目と幅を調節して切ります。
この際に仮置きした順番に番号を付けておくと、後で張る順番が分かりやすいです。
4.フローリング材を張る
これでようやくフローリング材を張れます。
フローリング材の端の凸凹をかませながらボンドで貼り付けていきます。
そのあと、ゴムハンマーでたたいて圧着させて、釘で固定します。
5.(任意)コーキング剤と巾木(はばき)で隙間を埋める
床と壁の間の隙間をコーキング剤や巾木で埋めて完成です。